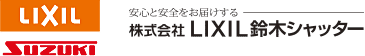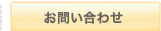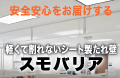危害防止機構(危害防止装置)に関連する法規資料
平成17年12月1日から防火/防煙シャッターの危害防止機構の設置が義務付けられました!
平成16年6月に防火シャッターに児童が挟まれる重大事故が発生しました。これを受け防火シャッター等の防火設備に挟まれることにより、人が重大な危害を受けることがないようにするため、平成17年12月1日より閉鎖作動時の危害防止機構等の設置が義務付けられました。
危害防止機構※1は防火シャッター用の、非常時における挟まれ防止の安全装置で、感知器連動でシャッターが自重降下している時あるいは手動閉鎖装置でシャッターが自重降下している時に機能し、障害物がなくなると再度降下し全閉します。(この場合、非常電源として蓄電池が必要になります。)
※1危害防止機構は、座板感知部、危害防止用連動中継器、自動閉鎖装置または手動閉鎖装置を組み合わせて防火シャッター等挟まれた人に危害が及ばないようにする仕組みです。
設置を義務付けられた危害防止機構等として次のようなものがあります
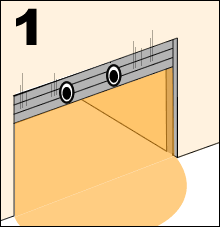
シャッターが降下途中に…
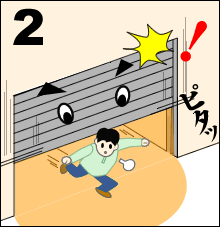
シャッターの座板に人が接触した場合、即座に降下停止!
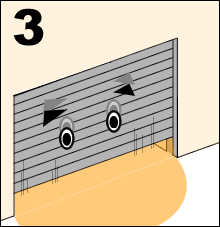
接触がなくなってから一定時間後に降下を自動再開→シャッター全閉。
なお、吹き抜けに設ける防火シャッターなど、人が通行の用に供することがなく、したがって安全が確保されているとみなされる場合については、規制対象となりません。
- 参考資料1 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成17年7月21日政令第246号)
-
- 第112条(略)
- 2.〜13.(略)
- 14.第1項から第5項まで、第8項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
- 一.第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
- イ.(略)
- ロ.開閉又は作動するに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
- ハ.(略)
- 二.(略)
- 二.第1項第二号、第4項、第8項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
- イ.前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
- ロ.(略)
- 一.第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
- 15.16.(略)
- 参考資料2 改正建築基準法施行令・告示(建告第2563号、同第2564号)の主な内容
-
- 通行の用に供する部分に設けるすべての防火設備(防火シャッター、防火ドア、耐火クロス製防火・防煙スクリーン、昇降路の出入り口の戸など)を対象とする。
- 周囲の人の生命又は身体に重大な危害が及ぶおそれがないことを要求性能とする。
- 具体的には、1.及び2.の条件を満たすものであることとする。
- (1)閉鎖作動時の運動エネルギー((1/2)MV2)が10J※1以下であること。M:防火設備の質量(kg)V:防火設備の閉鎖作動時の速度(m/s)計算例※2
- (2)防火設備の重量が15kg以下であること。(質量が15kgを超える場合は、水平方向に閉鎖するもので閉じ力が150Nであること、又は周囲の人と接触した場合に5cm以内で停止すること。)
※1 J(ジュール)とはエネルギーの単位で、1N(ニュートン)の力で、ある方向に物体を1m動かすのに必要なエネルギーであるが、動いている物体が持っている運動エネルギーもこの単位で測られる。
※2 計算例:W 5m×H 2.5mの防火シャッターの場合
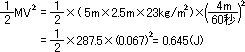
- 参考資料3 危害防止機構の全体構成図
- 危害防止用連動中継器の蓄電池は、消耗品ですので交換が必要です。
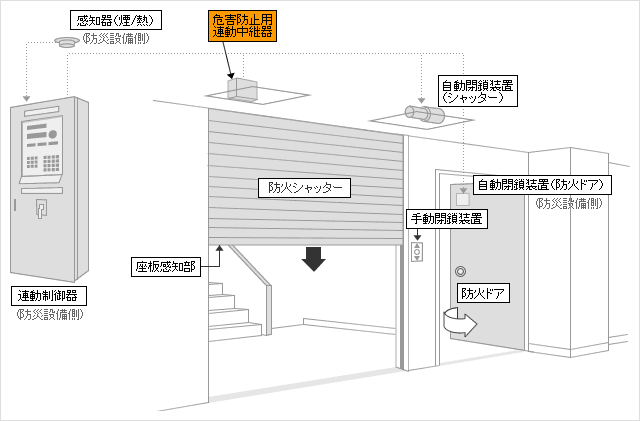
- お問い合わせはこちらまで
- info@lixil-suzuki.co.jp
※メーラーが立ち上がります。