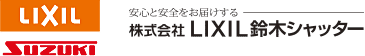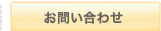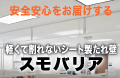シャッターの歴史
災害が、シャッターを強くした。
| 1837年(天保8年) | シャッターの祖形となる木片をつづり合わせた木製シャッターがイギリスで作られる |
|---|---|
| 1862年(文久3年) | ロンドン大博覧会に木製シャッターが出品される |
| 1872年(明治5年) | クラーク・バーネット(英)、スチール・シャッターの特許申請 |
| 1896年(明治29年) | 日本で最初のシャッター(英国製)が日銀本店に取付けられる この建物の開口部に用いられたのがスチール・シャッター、スチール・サッシで、イギリスより輸入されたものでした。(シャッターという言葉は英語のshutterが語源です)当時シャッターは「畳込防火鉄戸」、サッシは「鉄枠鉄障子」と呼ばれていました。20世紀に入るとインターロッキング形シャッターが登場し100年経た今日なお、シャッターの主流となっています。 |
| 1903年(明治36年) | 鈴木シャッターの前身である建築金物商会(創立者:鈴木富太郎)が創立。国産スチール・シャッター誕生 明治30年代に入ると洋式建築にはシャッター、サッシ、ドア等の輸入建築金物が用いられるようになり、専門の建築材料輸入販売業者が現れ始めました。 |
| 1906年(明治39年) | サンフランシスコ大地震発生。スチール・シャッターの防火性能に注目される |
| 1910年(明治43年) | 建築金物商会、自社工場建設。シャッターの自社製作を始める |
| 1914年(大正3年) | 国産スチール・サッシ誕生。第一次大戦によりシャッター、サッシの輸入ストップ |
| 1920年(大正9年) | 「市街地建築物法」施行される。シャッターの法的地位を得る |
| 1923年(大正12年) | 関東大震災発生。国産シャッターへの見直しとなる シャッターの防火における有効性が認識され、シャッターは広く普及するようになりました。 |
| 1932年(昭和7年) | 白木屋に大火発生。防火区画規定の引き金になる 昭和7年、日本橋白木屋の火災をきっかけに「百貨店規制」が告示されました。 |
| 1933年(昭和8年) | 1500m2区画、階段区画の警視庁令告示 1500m2以内毎の防火区画、階段区画が規定され、今日的な防火シャッターの使われ方となりました。 |
| 1934年(昭和9年) | 室戸台風。推定瞬間最大風速値60m/sec。耐風圧強度規定の動きとなる |
| 1939年(昭和14年) | 建築金物商会、鈴木シヤタア工業(株)に社名変更 |
| 1948年(昭和23年) | 建設省設立 |
| 1950年(昭和25年) | 建築基準法、施行される シャッターとの関連が密接なものとしては耐火建築物、特殊建築物の規定がもりこまれ、全国一律に適用されました。 |
| 1955年(昭和30年) | 軽量シャッターメーカーの創立相次ぐ 昭和30年代に入ると軽量シャッターが急伸し関西を中心に軽量シャッター・メーカーが続々誕生しました。 |
| 1969年(昭和44年) | 建築基準法施行令の一部改正。シャッターの自動閉鎖の規定 |
| 1972年(昭和47年) | 大阪千日前デパート火災、死者118名。防煙シャッターに対する社会的要請強まる |
| 1973年(昭和48年) | 熊本大洋デパート火災、死者103名 建築基準法施行令の一部改正(建設省告示第2564号)。竪穴区画の遮煙義務が課せられる 相次ぐデパート火災で煙により多数の死者が出たことから、建設省告示によって遮煙性能を有するシャッターが規定されました。これが防煙・防火シャッター(略して防煙シャッター)です。現在、防煙シャッターの生産量は、重量シャッターの全生産量の約1/2を占めています。 |
| 1990年(平成2年) | 建築基準法施行令の一部改正(建設省告示第1125号) 甲防の性能試験方法により、鉄製以外の製品が可能になりました。 |
| 1995年(平成7年) | PL法(製造物責任法)施行。障害物感知装置等の標準化 |
| 1998年(平成10年) | 煙感知器連動防火シャッターの挟まれ事故死発生 防火シャッター閉鎖作動時の危害防止に関するガイドラインが策定される。 |
| 2000年(平成12年) | 建築基準法の改正 防火シャッターの性能規定化。 |
| 2005年(平成17年) | 建築基準法施行令の一部改正。 防火シャッターに危害防止機構の設置が義務付けられる。 |